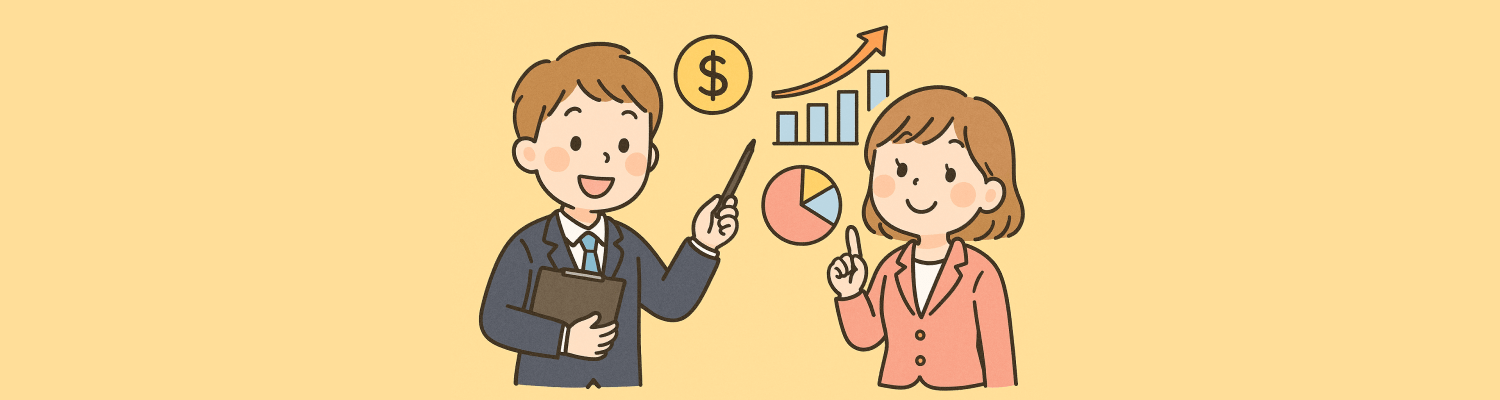特定の商品を保証する投資助言はできない

FP資格を取って、お客さんの役に立ちたい。そう思って勉強を始める人は多いでしょう。でも実際に仕事を始めると、思ったより「できないこと」が多いことに気づきます。特に投資関連の相談で、具体的な銘柄を勧められないという制限は、かなり大きな壁です。
「この投資信託がいいですよ」と言いたくても言えない。お客さんから「どの株を買えばいいですか」と聞かれても答えられない。FPになったからといって、自由に投資アドバイスができるわけじゃないんです。
FPが個別銘柄を推奨できない理由
なぜ具体的な商品を勧められないのか。それは金融商品取引法で投資助言・代理業の登録が必要と定められているからです。
投資助言業に該当する行為とは
金融商品取引法では、有価証券の価値分析に基づいて投資判断を助言する場合、投資助言・代理業として内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。つまり、FP資格だけでは法的に不十分なわけです。
具体的に禁止されているのは、こんな助言です。
- 「株式Aを買ったらいいでしょう」という特定銘柄の推奨
- 「投資信託Bをポートフォリオに組み入れましょう」という具体的な組入提案
- 「このインデックスETFがおすすめです」といった商品選定
- 「公社債を30%組み入れてください」のような具体的な割合指示
日本FP協会も会員向けパンフレットで、「投資助言・代理業の資格がなければ、具体的なプランや投資先のアドバイスをすることはできません」と明記しています。
違反した場合のリスク
無登録で投資助言を行えば、金融商品取引法違反として処罰対象になります。金融庁のウェブサイトには無登録業者のリストが188ページにも及んで公開されているほど、厳しく監視されている分野です。軽い気持ちで「これがいいですよ」と言ってしまうと、後で大きな問題になりかねません。
FPができる投資関連業務の範囲
では何も話せないのかというと、そうではありません。一般論の範囲内なら問題ないんです。
許される情報提供の具体例
投資助言業の登録なしでも、こんな対応ならできます。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 「株式と債券を組み合わせるとリスク分散になります」 | 「あなたは株式30%、債券70%で組みましょう」 |
| 「NISAは年間360万円まで投資できます」 | 「この投資信託をNISAで買ってください」 |
| 「インデックスファンドは低コストが魅力です」 | 「このインデックスファンドがおすすめです」 |
| 「長期・分散・積立が投資の基本です」 | 「この3つの銘柄に分散投資しましょう」 |
グレーゾーンの判断が難しい
実際の相談現場では、どこまで踏み込んでいいか迷う場面が多々あります。「複数の資産クラスに分散すべきです」は一般論だからOK。でも「国内株式30%、外国株式20%で」と具体的な割合を示すのはグレー。このラインの見極めが本当に難しい。
お客さんは具体的な答えを求めて相談に来ているのに、「それは答えられません」と言わざるを得ない。このもどかしさは、FPとして活動する上で常につきまとう悩みです。
投資助言をするための選択肢
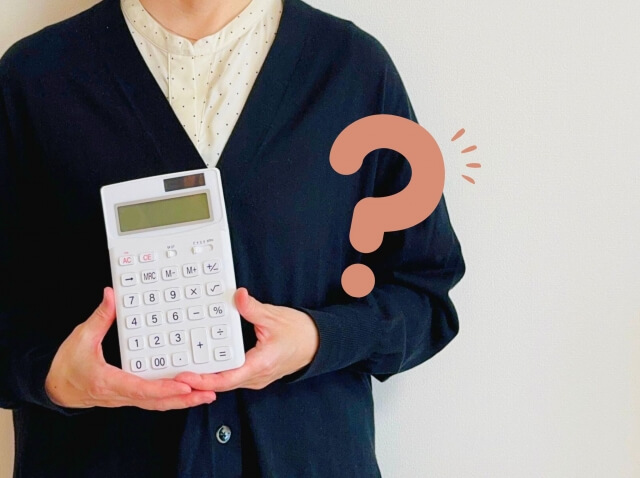
どうしても具体的な銘柄助言をしたいなら、道は二つあります。
投資助言・代理業の登録を取る
一つ目は、投資助言・代理業として金融庁に登録すること。これで法的に問題なく個別銘柄の推奨ができるようになります。ただし、登録のハードルは低くありません。体制整備や人的要件など、クリアすべき条件が多数あります。
それに、投資助言業は本来、機関投資家向けのビジネスモデル。個人顧客相手に採算を取るには、年間20~30万円程度の顧問料、または管理資産の1%程度のフィーが必要になってきます。
金融商品仲介業者として活動する
二つ目は、金融商品仲介業の資格を取得すること。証券会社などの委託を受けて、取扱商品ラインナップの中から提案できる立場になれます。ただし、あくまで「取扱商品の中から」という制限つき。世の中すべての商品を自由に提案できるわけじゃありません。
FPとして守るべきラインと向き合い方
法律の制限があるからこそ、できる範囲で最大限の価値を提供する。これがFPの役割だと思っています。
顧客の期待とのギャップをどう埋めるか
正直、お客さんの期待に応えられないことはつらい。でも、投資者保護のための規制である以上、守らなければならないラインです。誰でも自由に銘柄推奨できる状況になれば、それこそトラブルだらけになるでしょう。
だからこそ、投資の考え方や判断基準をしっかり伝えて、お客さん自身が選べるようにサポートする。商品名は言えなくても、選び方の軸を示すことはできる。地味だけど、これがFPにできる誠実な対応だと考えています。
具体的な銘柄選定が必要なら、投資助言業の登録を持つ専門家や金融商品仲介業者を紹介する。自分のできる範囲を理解して、適切に連携していく。そういう姿勢が、FPとして長く活動していくには必要なんです。